食べて学べて楽しめる!
「伯方の塩」の工場へ
行ってみた。

「は・か・た・の・しお♪」のサウンドロゴでお馴染みの伯方の塩。おそらく全国で最も有名なあの塩は、実は今治の伯方塩業株式会社がつくっています。
「え、福岡の博多だと思っていた!」なんて方もなかにはいるのですが、伯方塩業は、かつて塩つくりが盛んだった瀬戸内海に浮かぶ伯方島で創業し、2023年にはなんと50周年を迎えた老舗メーカーです。そこで今回は、塩の歴史を学ぶため、伯方塩業株式会社大三島工場へ見学に来てみました。
工場の入口にはあのCMジングルを奏でられるチャイムが。今治タオル工業組合の岡本佳代子さんがトライしてみました。

意外と難しい!知っている曲だけに、リズムが違うとすぐにバレてしまいます。正しいリズムで叩こうと夢中になってしまいますね。
塩つくり体験に挑戦!
さらに大三島工場では、塩つくり体験の無料プログラム(要予約)も。今回は、岡本さんが体験します。

塩つくり体験に挑戦!
つくり方を解説していただくのは、伯方塩業の赤瀬秀明さん。

テーブルの上には、ガスコンロと小さな土鍋、そしてペットボトルが置いてありました。このペットボトルに入っているのが、伯方の塩の原料と同じ濃い塩水(かん水)なのです。これを土鍋に移し、水分を蒸発させながら塩つくりを行います。
まずは、ペットボトルを開けて、土鍋に全部入れます。

それから濃い塩水をちょっと味見します。海水と比べて、どんな味がしますか?

「濃い!かなりしょっぱいです」と岡本さん。
「普通の海水だと約3%の塩分濃度なんですが、これはその8倍以上の濃度で、24%〜25%ぐらいあります。人それぞれ味覚が違うので、しょっぱいという人もいれば、すごくおいしいという人もいるし、そんなに海水と変わらないという人もいるんですけど」(赤瀬さん)
では、火をつけてみましょう。沸騰しはじめたら、竹べらで混ぜます。


塩がハネるのでゴーグルを装着
土鍋のふちにだんだん塩ができてきましたね! パチパチとはじける塩に注意しながら混ぜていきます。

そんな感じで加熱を続けると、10分くらいで煮詰まってきました。


水分がなくなってくると、だんだんふっくらとした塩になってきました。焼きつかないように丁寧にかき混ぜます。


そしてできた塩はスプーンでお皿に移します。すごくサラサラでおいしそうな塩が完成しました!
つくった塩は、少し冷ました後、チャックのついた袋に入れて持ち帰ることができます。


「楽しかった!」と大満足の岡本さん
短時間でしたがとても楽しい体験ができましたね。この塩つくり体験の申し込みは多いんですか?
「はい、とても人気ですぐに予約が埋まりますね。一週間前までに電話予約を入れていただければと思います」(赤瀬さん)
大相撲や有名飲食店でも、
伯方の塩を使用
さて、それでは工場見学に行ってみましょうか。まずは、5月にリニューアルしたばかりの見学通路から。今回、伯方塩業の野間保さんに案内していただきました。毎日、見学の方ってどれくらいいらっしゃるんですか?

「そうですね。多い時は何百人単位でいらっしゃいます。三連休の中日だと1,000人近くになりますね」
え?そんなに?!かなり人気の観光スポットなんですね。
「ありがとうございます。今治の有名飲食店の大将やシェフの方もたまにいらっしゃいますよ。ここの塩を使っていただいているので」
なるほど…!それはぜひ買って帰りたいですね。
2階に上がってすぐに目についたのが、見学通路にある相撲コーナー。確かに相撲では塩をまいていますね。あれって伯方の塩なんですか?

見学通路にある大相撲コーナー
「はい。大相撲の東京場所と名古屋場所で使われている塩は、伯方の塩なんです。また、2022年からは、日本相撲協会のオフィシャルスポンサーになっているんですよ」
2009年に行われた、愛媛県出身の力士・玉春日(現・片男波親方)の断髪式の際には、伯方塩業の会長が出席したとか。とても縁が深いんですね。
5万人の署名が!
消費者運動から生まれた塩
そして、まず案内されたのが、大量に塩が置いてある場所。わあ、雪山みたいですね。

「ここに積まれているのは、伯方の塩の原料の一つであるメキシコとオーストラリアの天日塩田塩です」
え、塩って、今治の海水でつくってるわけじゃないんですか?!
「『伯方の塩』の原料に輸入した天日塩田塩を使っているのは、法律が深くかかわっているんです」
ええっ!? 法律ですか?
実はここに、「伯方の塩」誕生のストーリーがありました。
まず、日本の塩つくりの歴史を。縄文・弥生時代は海水をそのまま煮詰める「直煮(じきに)製塩」で塩をつくっていました。海水の塩分濃度は約3%なので、より効率的に塩をつくるため、塩田を利用するようになりました。室町時代には「揚浜式塩田製塩」が開発され、いまでも石川県の能登半島ではこの方法で塩つくりしている場所があります。

伯方の塩の歴史がわかるコーナー
江戸時代には「入浜式塩田製塩」が行われるようになり、さらに1953年には「流下式枝条架併用(りゅうかしきしじょうかへいよう)塩田製塩」が主流となりました。瀬戸内海沿岸には多数の流下式枝条架併用塩田が立ち並び、塩つくりが盛んに行われていました。当時の塩は、日本の製塩史上、最も食用に優れていたと言われていました。
しかし、塩田での塩つくりは、天候に左右され農耕的な作業が多く、人手が掛かっていました。

1971年、全国の塩田は近代化を推進する「塩業近代化臨時措置法」によって全廃。品質よりも生産効率を優先したイオン交換膜を利用してつくる塩に切り替わることになりました。この塩は世界でも食用にした前例がなく、安全性が十分に確かめられていませんでした。
また、当時は「塩専売法」という法律のもと、国が管理していたので、民間の会社は自由に塩をつくることができませんでした。そこで、愛媛県在住の5人の消費者が中心となり、塩の選択権と塩田の存続を求めて運動を展開しました。その活動は全国に広まり、5万人の署名を集め、国を動かす大きな運動へ発展していきました。
「運動の結果、塩田を残すことはできなかったのですが、当時、国がメキシコやオーストラリアから輸入していた天日塩田塩を原料にする、海水から直接塩をつくってはいけないなどの厳しい条件の下で、安心して食べられる塩をつくることが許されたんです」(野間さん)
そして1973年12月、流下式枝条架併用塩田を利用してつくられた塩を手本に、にがりをほどよく残した「伯方の塩」が誕生。その名前には「伯方島の塩田を復活させたい」という人々の願いが込められていました。
なんと、伯方の塩には、そんな歴史があったんですね。歴史をかみしめながら、伯方の塩の製造工程の見学に戻りましょう。
塩つくりの
ステップを見学
塩つくりのステップは、以下の通り。まずは、「溶解・ろ過」。
「輸入した天日塩田塩を、日本の海水で溶かして濃い塩水をつくります。天日塩田塩は、屋外で1~2年ほどかけて塩を結晶させるので、どうしても砂などが混じったりします。そのため海水で完全に溶かしてろ過するんです。また天日塩田塩にはにがりがほとんど含まれていないため、海水に溶かすことでにがりを含ませています」
ものすごい量ですね。

次に「煮詰める」工程です。濃い塩水を釜で数時間かけ煮詰めて塩を結晶化させます。

そして「自然乾燥」。にがりをほどよく残すため、数日間かけてゆっくりと自然乾燥させます。
「塩は、金属の錆びを進めますので、ここの座面や壁に使われている金属は、錆に強いチタン製を採用しています」(野間さん)

「にがりは“苦汁”と書き、文字通り苦味が強いものです。多すぎても良くないので、ほどよく残すことが、当社のこだわりの一つです」(野間さん)
それから「選別・袋詰め」し、最後に「目視検査」。機械でも異物混入対策を徹底していますが、加えて一つずつ丁寧に人の目で異物や汚れがないかを厳しくチェックし、箱詰めをして行きます。こうしてできた伯方の塩が、全国へ届けられるのです。
社員みんなの手で
再現させた塩田

竹の枝を組んだ「枝条架」と
その両端にある「流下盤」
1997年に「塩専売法」が廃止され、再び日本の海水から直接塩をつくれるようになりました。
そこで、塩田に関する技術を社員が習得し、次世代に当時の品質・味わいを継承しなければならないとの想いから、「流下式枝条架併用塩田」を再現し、塩田を利用した塩つくりを決意したそうです。そうして2005年に、プロジェクトを発足。試行錯誤の末、2010年に大三島工場の敷地内に再現されました。
さて、ここからは、再び赤瀬さんに案内していただきます。よろしくお願いいたします。
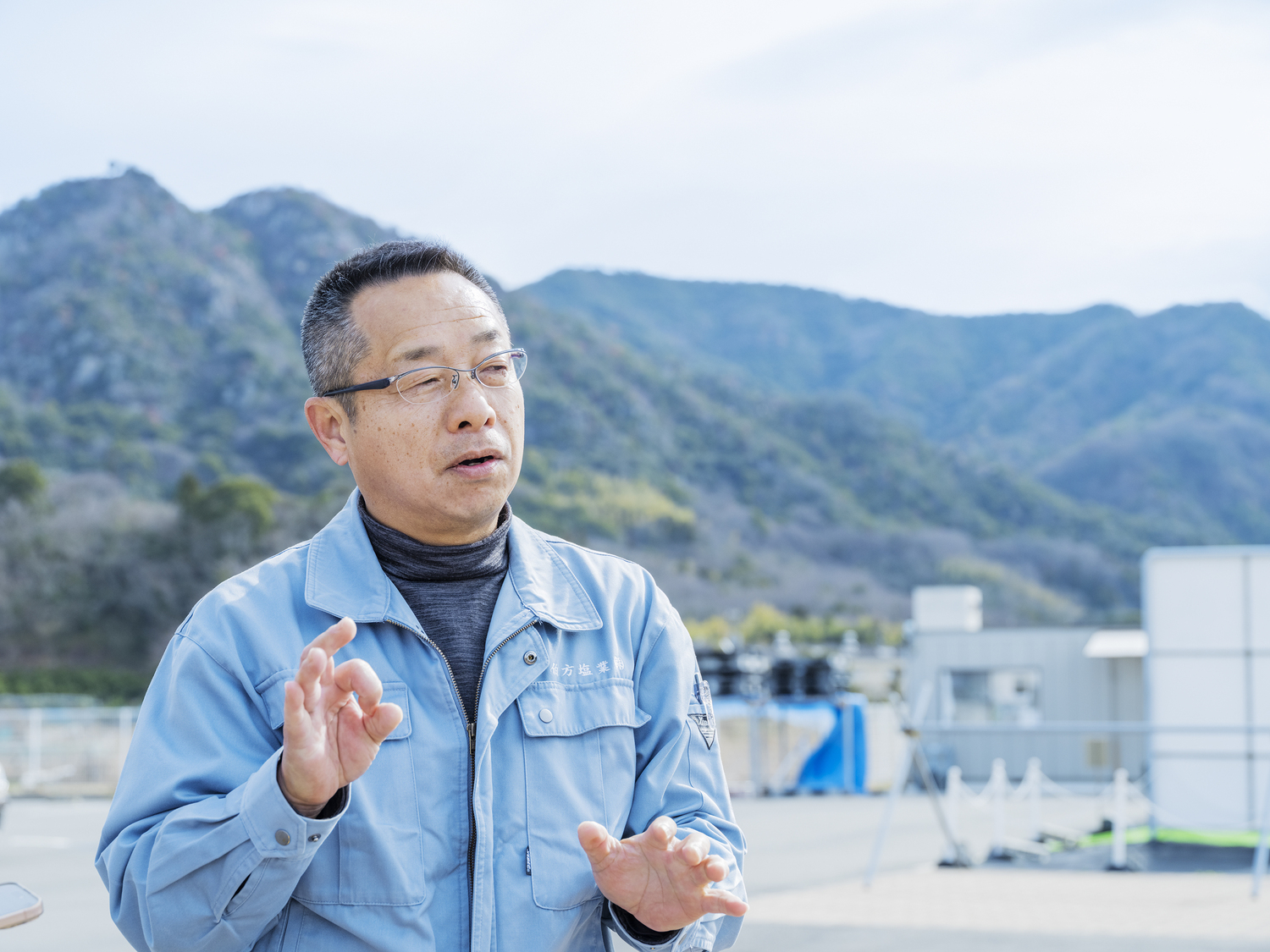
「よろしくお願いします。この塩田は流下式枝条架併用塩田と言います。この両端にあるのが流下盤。海水を流して、太陽の熱を利用して水分を蒸発させて塩分濃度を上げます。その後竹の枝を組んだ「枝条架」の上から滴り落とし、風の力でさらに濃縮させます。この工程を繰り返してできた濃い塩水を煮詰めて塩をつくります」(赤瀬さん)
自然の力で濃い塩水をつくっているんですね。
「そうなんです。海外では岩塩などの塩資源もあるんですが、日本は雨が多く湿度も高いため、天日の力だけで塩をつくることが難しいため、海水を濃い塩水にしてから煮詰めて塩をつくるようになりました」
ちなみに、先ほど工場で見せていただいた伯方の塩と、どのような味の違いがあるんですか?
「つくり方は違いますが、成分や味の違いはそんなにないです」
なるほど。この塩田は社員の皆さんが手づくりで建てたと聞いたのですが?
「はい。プロジェクトを結成しまして、隣の伯方島に当時の塩田に携わられた方がいたので、その人の話を聞きながら建てました。当時の文献とかそういうのが少なかったんでね」
よく覚えてらしたんですね!
「そうですね。長年携わってらしたので。建て方だけじゃなくて、運転の仕方とか、メンテナンスの仕方とかも教わりながらやりました」
この塩田でできた濃い塩水からは、どれぐらいの量の塩がつくれるんですか?
「年間15トンほどです。」
昔ながらの製法なので手間がかかるんですね。
こうしてできた塩は「されど塩」という商品で販売されているのですが、この大三島工場と、公式のネットショップなど、ごく限られた場所でしか購入できないとか。これはぜひお土産に買って帰りたいですね。

塩の力でおいしくなった!
ソフトクリームとコーヒー
見学の後は、工場1階のショップで塩ソフトクリームをいただきました。
「めっちゃおいしいです!塩が入っていて甘味が引き立ちますね」(岡本さん)
このソフトクリーム、甘めのミルクと塩の相性がよく、伯方の塩を使った商品のなかでもダントツ人気。以前はこの工場限定だったのですが、JR松山駅にオープンしたコンセプトショップ「with salt 伯方の塩」でも食べられるそうです。

一緒に買ったコーヒーも飲んでみました。
「最初は塩を入れずに飲んで、次に塩をちょっとだけ入れてみてください」と野間さん。
言われたとおりにしてみると…おいしい。確かに塩を入れたらマイルドになりますね!
「入れなくてもおいしいんですけど、味がガラッと変わりますね。びっくりしました」(岡本さん)

コーヒーに塩を少し入れるとマイルドな味に
「塩を入れない状態の方がガツンとくる味わいなので、どちらが好きかは人それぞれかもしれませんが、塩を少し入れるだけでマイルドになるんですよね」(野間さん)
塩のポテンシャルってすごいんですね!
最後に1階のショップでお土産を買って帰りましょう。

ショップには、先ほどの「されど塩」や定番の「伯方の塩」のほか、伯方の塩を使ったお菓子などもたくさん並んでいました。さらに、大三島の耕作放棄地を活用した自社農園(GOENファーム)で、有機栽培したさつまいもなども売っていました。

5月にリニューアルして、より一層おもしろくなった「伯方の塩」の工場。行ったことのある方も、初めての方も、大三島に来たらぜひ寄ってみてくださいね。
伯方塩業株式会社
https://www.hakatanoshio.co.jp/
工場見学・塩つくり体験予約
https://www.hakatanoshio.co.jp/factory/
with salt 伯方の塩
https://www.instagram.com/with_salt_hakatanoshio/